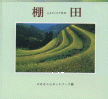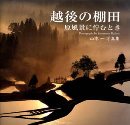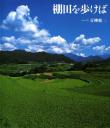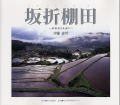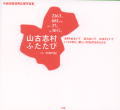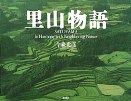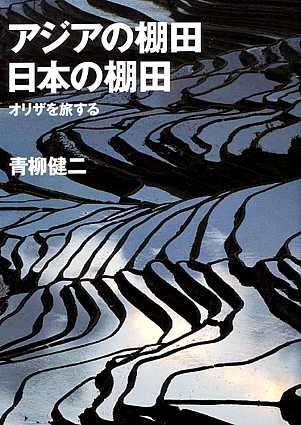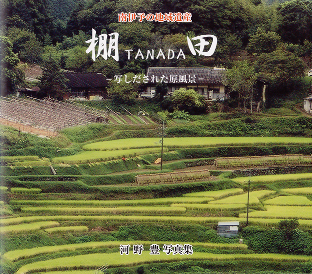図書等
写真集
このページの先頭に戻る |